第1章 好きなことを見つける
ここはタール村。ごく平凡な村であり、少しの畑と、あとの男たちは街へ出稼ぎに出て、生計を立てていた。
近くには川が流れ、田舎も段々と都会化している中では、自然が多い村であった。
そこに、ある男がいた。名前をクウという。心優しい青年で、誰からも人気があった。
クウは争いを好まない人間で、人の悪口も言わない男であった。少し優しすぎるくらいであった。
クウは、皮製品を売る仕事をしていた。皮というのは汎用性が高い材料で、皮をなめして鎧にしたり、手を守る小手にしたり、普段使いでも財布にしたりと、色々な用途に使えた。
そんな色々な用途に用いられる皮製品であれば、色々な人の役に立てるのではないか、そう思って、青年クウはその仕事を選んだのである。
皮製品を作る職人がいる場所は、タール村から少し離れたコンコルド街というところにあった。コンコルド街の、「チョウリ」という場所が、クウの職場であった。
クウは歩いてその街まで行って、皮製品を受け取り、各村にその製品を売る仕事をしていた。
しかし働き始めてしばらく経って、クウは段々とその仕事に意味を見出せなくなってしまっていた。
まず皮製品を売る場所は、クウが働いているチョウリ以外にもいくつもあった。すでに職人の技術はあまり差がつかなくなっており、なかなか他のところと差別化がつかなくなってきていた。
そんな中、チョウリで作った皮製品をちゃんと売ることは至難の技であった。それに皮製品はすでに流通し、若干飽和状態にあったため、あまりお客さんもその皮製品を重要視している感触がなく、どうしても値段が安くないと売れないという事態に陥っていたのであった。
元々クウは皮製品であれば、いろんな人に喜んでもらえるのではないかという思いで始めていたので、それがなかなか満たされず、悶々としていたのであった。
そんな時、コンコルド街を離れ、近くの村まで皮製品を売る途中、小さな川があったので、川辺に腰を下ろし、少し休むことにした。
クウが住んでいるタール村にも、川が流れており、同じような川を見ると、早く家に帰って休みたい。そんなふうに思うのであった。
この仕事を辞めようか。
そんな思いに駆られたのも一度や二度ではなかった。いったい全体、ここからどうやっていけばいいのか。
そうしてふと横を見ると、クウと同じように、川辺に腰を下ろしている男の人がいた。
クウより少し上の世代で、あまりこの辺りでは見ない顔であった。髭を蓄え、優しい目をしているのが印象的であった。
「綺麗な川ですね」
その男性はそう言った。
「そうですね」
クウも答えた。
「差し出がましい話かも知れませんが、元気がないようにお見受けします」
その男性は優しい目でそうクウに話しかけた。
「はは、そうですか、お恥ずかしい。いえ、仕事がうまく行ってなくてですね。こう言って、道草を食っているわけです」
クウは正直にそう言った。クウは心優しい青年であったが、あまり自分の話はしない人間であった。自分の話をすると少し愚痴っぽくなってしまう気がして、それで自分の話は極力しないようにしていた。
しかしこの男性には自分を打ち明けても、それを受け止めてくれそうな雰囲気があった。
「僕はケーと言います。学校で教師をしているんです。今日は久しぶりのお休みだったので、こうして好きな自然と遊んでいるわけです」
ケーと名乗ったその男性はそう話した。
「最近、子どもたちも元気がありません。なんだか目がうつろと言いますか。夢を失っている気がするんです。僕はそんな子どもたちを見ていると、どうにかしてあげたいと思うんです。もっと世の中楽しいもんだ。だからそんな目をしないで、と」
ケーは悲哀を感じる顔でそういった。
「そうなんですね、、、あ、あと、ぼくはクウと言います。皮でできた製品を売る仕事をしています。今は休憩していたところです」
クウも名乗った。そして珍しく自分のことを話し出した。
「いきなり会った人にこんな話をするのもおかしな話ですが、、、ぼくも最近なんだか元気がないんです。好きで始めた仕事だったはずなのに、なんだかうまくいかなくて・・・。自信も持てないんです」
クウはそう言うと、少し泣き出しそうになってしまった。自分が情けなく、ダメな人間に思えてきてしまった。
ケーはクウに質問した。
「今のお仕事はどういうきっかけで始められたんですか?」
「もともと人の役に立つ仕事がしたくて始めたんです。皮って色々な用途で使えるので、たくさんの人に喜んでもらえるかなって。でも現実はそんなに甘くなくて、安くないと売れないし、皮製品なんて当たり前すぎてお客さんもあんまり喜んでくれなくて。ぼくのやり方がまずいのかも知れないんですけどね」
「なるほど・・・。」
ケーは真剣な目でクウの話を聞いてくれた。
「なかなか思い通りにはいかないものですよね。僕も子どもたちに必死になって思いを届けようとしますが、なかなか伝わりません。ちなみに・・・」
ケーはもう一度クウのことを見て、言った。
「クウさんの好きなことってなんですか?」
「えっ」
クウは少し面食らってしまった。好きなこと?
「クウさんは先ほど『人の役に立ちたくて』、今の仕事を始められたとおっしゃっていました。それは仕事を始めた”動機”だと思います。それは素晴らしい動機であると思います。しかしそこから離れて、好きなこと、子供の頃好きだったこととか、趣味で続けていることとか、何かありますか」
そう聞かれて、返答に困ってしまった。なぜならそう言ったものが一つも見当たらなかったからだ。
もちろんタール村の図書館にある本を読むことは好きだし、コンコルド街に唯一ある劇場にたまに足を運んで楽しむことはある。しかし「これが好きだ!」と言えるものが何一つないことに気づいた。
返答ができていないと、ケーは困った顔をして言った。
「スミマセン、なんだか詰問するみたいな感じになっちゃって。これは僕が生徒たちによく聞くことなんです。君の好きなことはなんなんですかってね。今の生徒たちは変に優秀というか、非の打ち所がない応対をする子が多いんです。しっかりと勉強して大きな街に行って、そこで王様の役に立つような人になるとか、はたまたお金持ちになるんだとかね。でもそれは”なりたい”自分であって、もっと根源的なところで、自分は何が好きなのかと言うことをもっと深堀りした方がいいと思うんです」
ケーは真剣な眼差しでそう言った。
「何が好きか・・・ですか。正直あまり考えたことはなかったですね。いわゆる”趣味”みたいなものなんですかね。」
趣味は道楽ではないけれども、正直役に立たないもの、お金を生み出さないものと思ってきた。好きかどうかと言うよりも、お金が稼げるかの方が非常に重要だと思ってきた。
「ぼくは、好きなことと聞かれて、お恥ずかしながら、はっきりとこれだ!と言えるものがありません」
クウはしょんぼりした顔でそう答えた。それにケーはニカっと笑って答えた。
「大丈夫ですよ。実は好きなことを見つけるコツがあります」
「えっ、そうなんですか?それってなんなんです?」
いつの間にか、クウは身を乗り出していた。
「自分を信じることです」
「自分を信じる?」
これまた抽象的な答えだなとクウは思った。
「スミマセン、ちょっと抽象的すぎましたね。詳しく言うと、自分を信じて、なんでもいいから面白そうだな、楽しそうだなと思ったことをやってみることです」
「なんでもいいからやってみる・・・ですか」
クウは考えた。
「そう言った意味だと、今ぼくは川辺にふらっとやってきましたが、意識してみると、こういった川とか自然が好きなのかも知れません。実はぼくが住んでいる村にも川がありましてね。うーん、そう言った意味だと家が好きということなのかなぁ」
「ふふ、そうですね。自然を好むのは人間の一般的な嗜好としてあると思います。その調子です!」
ケーは満面の笑みでそう答えた。気づけばけっこうな時間が過ぎていた。
「ケーさん、ありがとうございました。色々と参考になる話が聞けてよかったです。でもぼくはそろそろ仕事に戻らないと」
「クウさん、ありがとうございました。クウさんとお話しできてとても楽しかったです」
二人は自然と握手をした。
「またもし良かったらお会いしましょう」
「ええ、またこの川辺で」
そう言って、二人は分かれた。
クウは「好きなことを見つける」というスキルを身につけた!!

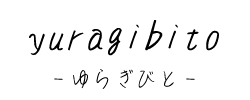








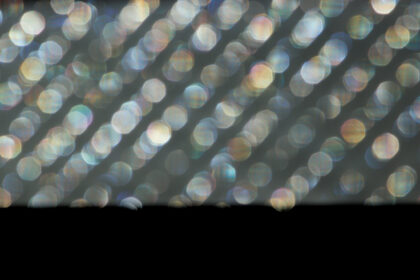

コメントを残す