第2章 稼げないとダメか
前回までのあらすじ
タール村の心優しい青年クウ。彼は皮製品を売る仕事で生計を立てていたが、自分の仕事に意味を見いだせなくなっていた。
そんな中、綺麗な小川の近くで会った、クウより少し年上の青年ケー。彼は村で子どもたちの教師をしているが、ケーはクウに、まず自分の好きなことを思い出すことを助言として残す。
クウはケーに言われた通り、まず自分の好きなことを探すのだが・・・。
自分の直感を信じる
クウはケーに言われたように、自分の好きなもの探しを始めてみた。
ケーは、まず自分の直感を信じ、やりたいと思ったことは、理由がなくてもいいからやらせてみることが重要ということを言っていた。
クウはまず自分が自然に多く惹かれていることを、客観的に発見した。
クウはタール村の自然が好きだったし、何より水や川を好んだ。なぜかゆらいでいる川の流れを見ると、心が落ち着くのであった。
そしていつしかその様子を絵に描くようになった。子どもの頃、絵を描くのが好きであったことを思い出した。今思えば、なぜあんなに夢中になっていたのに忘れてしまっていたんだろう。
絵を描くことは楽しかった。正直全然上手な絵ではなかったが、それで良かった。それに下手でもそれが徐々に上手になっていくことが感じられ、自分的には満足していた。
しかし、ここで疑問が頭をよぎった。その疑問を解消するため、またクウはケーに会うことにした。
意味がないといけないのか
「こんにちは」
やはりまた会えた。前にケーと会った川の近くに来てみたら、川辺に腰をかけたケーの姿があった。
今日はクウも仕事が休みで、前回ケーと会った場所に来てみたのだ。特段約束はしていなかったのだが、なんとなく今日そこにケーがいるような気がして、やってきたらやはりいたのだ。
「やあ、きみは、クウくんだったね、こんにちは」
ケーは非常に優しく、親しみやすい笑顔を携えて、クウに挨拶を返した。
「またお会いできて良かったです。実は少し相談したいことがあって・・・」
「相談したいこと?どうしたんですか」
ケーは眉をひそめ、心配そうな顔をして、クウの顔を覗き込んだ。
「実は先日アドバイスをもらった好きなもの探しで、なんとなく好きなことは見つかったのですが・・・」
「本当ですか!?それはおめでとうございます!ちなみに好きなことはなんだったのですか」
「自然を感じたり、絵を描くことが好きだったんです。絵は子どもの頃描いてたのですが、自分でも不思議なくらいすっかり忘れていて。」
「そうですか」
ケーはグッと親指を立てて、グッドサインを出してくれた。それも満面の笑顔つきで。
「ただ絵を描いているときにふと頭をよぎったんです。これって意味があるのかなって」
「意味ですか?」
「そうです、意味。結局絵を描くことは楽しいけど、それでお金が一銭でも入ってくるわけではないんです。逆に絵の具や紙を買わなければいけないのですから、お金的にはマイナスです。それに時間も使ってしまう。こんなことをしているより、自分の本業である皮製品の勉強でもした方がいいんじゃないかと思うのです」
クウは顔を曇らせながらそう言った。そうなのだ、絵を描くのは楽しい。それは事実だ。しかしそればっかりやっていても腹は膨れない。クウには奥さんと、子ども二人がいた。彼らを養わないといけない。そんな中遊んでいる暇はないのである。
「なるほど・・・要はそんな好きなことばっかりしてないで、仕事をした方がいいんじゃないかって、ことですかね」
「まぁ、そんなところです・・・」
「なるほどなるほど、僕はクウ君の気持ちがよくわかります。僕も昔はそう思っていました」
「えっ、そうなんですか」
クウは素直に驚いた。そして「昔は」と言っているため、今はもう解決しているかの口ぶりであることも。
「何か解決方法を編み出したんですか?」
クウは気になって、ケーに聞いてみた。
「僕が好きなことはキャンプなんですがね。キャンプというのは村にある家から離れ、一人で山に籠り、何日かたった一人で過ごすんです。テントを張って一人きり。食べ物も自分で調達する。まあ結構ワイルドな方かもしれない。で、僕も聞かれたんですよね、妻に。そんなことやって何か意味があるのと」
ぼくと同じ意見だ。クウは思った。
「その時僕はこう答えたんです。全く意味はない。僕が好きだからやっているんだって。あの時の妻の呆れ顔はいま見ても笑えますね」
そう言って、ケーは実に面白いと言った様子でケラケラと笑った。
「意味はない。意味はなくていいですか?」
「ええ、好きなことに意味なんてなくていいんです。そもそも意味なんて、人間が生きるためにプラスかマイナスかの基準で定義した物差しみたいなものです。しかし好きはそれを超越しています。好きなものは好き。それでいいじゃないですか」
確かにそう言われたらそうかもしれない。でもどうしてもクウは納得ができなかった。
「でも、ケーさん。好きなことばかりしてられないですよね。ケーさんも奥さんを養わないといけないし、キャンプばっかりしてられないですよね」
「もちろんです。仕事をして、お金を稼がないといけません。しかしそればっかりの人生でいいんでしょうか?僕は前も言ったかもしれませんが、学校で教師をしています。そこで僕は子どもたちに、好きなことはするな、お金が稼げる仕事だけをしなさいとは教えていません。できる限り自分の好きなことをしてそれを研究しなさいと教えています」
「確かに、子どもの頃は時間があるからいいでしょう。しかし大人になっても好きなことをするというのは・・・」
どうしても頭が拒否して仕方がなかった。それだけ好きなことをするというのは、クウとしては抵抗があった。
「いきなり人間の頭は切り替えられるものではないと思います。クウ君は、まず自分の好きなものを見つけた。まだ芽のようなものかもしれませんが、それを大事にしたらいいと思いますよ」
そう言ってケーは腰を上げて、お尻をパンパンとはたき、土を払った。
そして小石を取り上げて、川に向かって投げた。石は何回かバウンドして、最後は川の中に消えた。
「何かはやってみないとわからない。今僕は石を投げたけど、3回バウンドした。」
そう言って、ケーはもう一度石を投げた。今度は1回しか跳ねなかった。
「次は1回だったね。次はどうかな」
3回目。石はなんと6回も跳ねた。
「6回跳ねた!すごい」
「ははは、たまたまですよ。こういうふうに、何かはやってみないと、その結果はわからないものです。当たり前ですがね。好きなことも、やってみないとどうなるかわからない。」
クウははっとした。やってみないとわからない。それはそうだ。1回バウンドするか、2回バウンドするか、それとも6回バウンドするか、石は投げてみないとわからないように、ぼくが好きなこの絵も描いてみないとわからない。
描いていたら、何か起きるかもしれない。
「継続・・・なんですかね」
ケーは驚いた顔をして言った。
「そう、それがすごく重要なことなんです。それがすぐわかるなんて、クウ君はさすがですね」
「い、いや、それほどでも・・・。でもなんだかお話できて良かったです。ただ頭が少し疲れました」
「ええ、こういう話は頭を疲れさせます。なぜなら今までの常識が崩壊していくような感じですからね。でも今日はいい話ができたと思いますよ。また会いましょう」
そしてケーは颯爽と帰っていった。
一人取り残されたクウはボーと川の流れを見ていた。時折鳥たちが来て、その鳴き声が聞こえる。
やり・・・続けてみるか。
そう、クウは心の中でつぶやいた。
クウは、「継続する」のスキルを手に入れた!
以上。

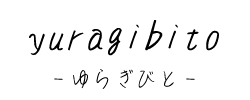








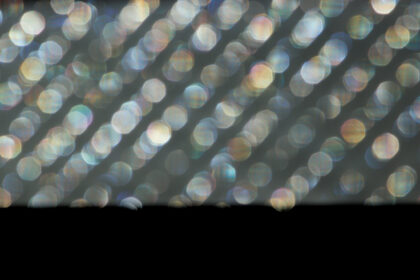

コメントを残す