(146)学習性無力感とはなにか
昔、こんな本を購入した。
「学習性無力感 パーソナル・コントロールの時代をひらく理論」
この本がびっくりするほど、読みにくい(笑)。翻訳がイケてないのかわからないが、自分にとっては非常に読みづらかった。
ただ、この本で論じている概念は、非常に参考になった。
学習性無力感とは、「あっ、これ以上力をかけても無駄だな」と人間理解すると、それ以上力を入れなくなるという、自動省エネ切り替え機能のことだと思う。
ラットの実験
色々と有名な動物実験はある。
箱の中にラットを入れて、ラットがいる床に微量な電流を一定間隔で流す。
最初、ラットは痛みを感じると、逃げ回ったり、キイッと鳴いたり反応を示すが、もうどうやってもこの痛みから逃れられないと感じると、微動だにせず、その痛みを許容するようになる。
その箱の横に、逃げ道を作ってあげても、もうそのラットは白旗をあげてしまっているので、逃げようともしないという。
なぜこんな行動を取ってしまうかというと、要は「やっても無駄だ」と思ってしまっているからだろう。何をやっても結果が同じであれば、やらない方がその体力を温存できる分効率がいいという脳の判断だ。
そのように脳が思ってしまっているため、それ以上考えることをやめてしまっている。脳で考えるのは非常に高エネルギーが必要で、脳が体重の2%ほどしかないのにも関わらず、全消費カロリーの20%を消費する大食らいなのだ。そんなコスパが悪い脳に対して、それ以上考えるなと、省エネ機能が発動してしまっているのだ。
老人ホームの例
冒頭の本で面白かったエピソードがあるので、1つだけ紹介したい。
それはとある老人ホームで、1階の入居者には、自己効用感を高めるため、観葉植物をいくつか用意し、自由に取って、自分で世話ができるようにセッティングした。また、映画の上映をするのだが、木曜か金曜のどちらがいいか決めて良いと伝えた。
一方2階の入居者に対しては、観葉植物の選択と飼育を全て職員側でやってしまった。また映画の上映日も職員側が決めてしまった。
こうなると、1階と2階の入居者では、態度が明らかに変わってきた。1階の入居者は活動的になり、気力も出て、抗うつ状態をほとんど示さなくなったという。
ここからわかることはなんだろうか。ここからは、自分で選択ができ、自分でコントロールができる事態になると、人は効用感を感じるということではないのだろうか。
老人ホームの1階の入居者は、自分で選んだ植物を、毎日育てるという仕事を得た。
また、映画の上映日を決められるという決定権を得た。
ぼくは、自己効用感を得るには、仕事と、決定権。この2つが重要であると考えている。
仕事とは、自分しかできないこと。自分がやることによって、この世界に影響を及ぼしているという効用感だと思う。また、決定権も、この世界になにか影響を及ぼすためのツールだと思う。
2階の入居者は舞台には上がらせてもらえず、あくまで観客のままの立場に置かれてしまったのだ。観劇していても、観客は舞台上の役者を見ることしかできない。舞台を作り出すのは役者の方だ。自分で作り出し、それが世界に影響を及ぼしていることを確認できないと、人間は自己効用感を感じることができない。
集団無視について
そう言った意味だと、「無視をする」「シカトをする」というのもかなり残酷な行為だということがわかる。しかもこれを集団でやるとタチが悪い。いじめも然りである。いじめられっ子は誰に話しかけても無視され、世界に自分が影響を及ぼすことができないと知る。こうなると、ラットの実験のように、無駄な行動を取らなくなり、消極的になり、抗うつ状態に陥る。
それでは、どうすれば、こういった抗うつ状態から抜け出せるのであろうか。
解決策は、仕事と決定権
答えは、先ほどの老人ホームの例で出た、「仕事」と「決定権」である。このセットが重要である。
仕事だけしていても、それが誰にも感謝されなかったりすると、この世界へ影響を及ぼせていないということで、ラットのように動かなくなってしまう。
一方決定権だけあったらどうか。たとえば宝くじが当たって5億円が懐に入り、なんでも自由にできるようになったら、どうであろうか。
最初はハイテンションになり、自分がやりたいことをやりまくるであろう。しかし自分の欲だけ満たしてもじきに虚しくなってくる。おれは何をやっているんだろうと。寂しいと。
これは世界に自分一人だけになって、神様になった時の気分と似ているだろう。神様なのでなんでもできる。天地も創造できる。しかしそれに対してリアクションを取ってくれる他者がいない。やはり人間は本能として、一人では生きられない、群れの生き物であることを痛感させられる。
自分にしかできない仕事をして、目的を得る。そして決定権。つまり自分がこの世界に関与、影響できることを信じている。この2つが揃った時、人は活き活きと生きられるのではないかと思う。
以上

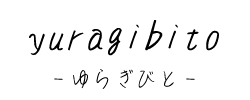








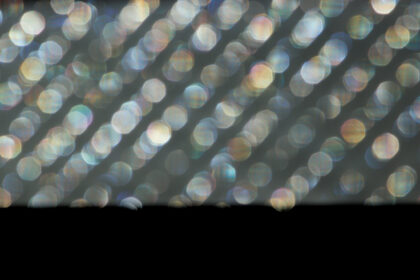

[…] 前回の記事で出てきた、「学習性無力感 パーソナル・コントロールの時代をひらく理論」にて、「随伴性」という言葉が出てくる。 […]