2.5章 夢を持てない、ハレ
この物語は、ある小さな村にある、ダンケ学校での、教師ケイと、生徒10人によるやり取りを記録したものである。
登場人物紹介
ケイ・・・ダンケ学校の教師。さまざまな経験から子どもたちに平等に、多種多様な事柄を教える。
ミド・・・ダンケ学校の生徒。賢く機転が効く。人のパーソナルスペースに土足で踏み込まない。
シバ・・・クラスの清掃委員。きれい好き。少し自分の意見を押し付けがち。
スイスイ・・・自分より他人を思いやる優しい子。最近、少し自分の意見を言えるようになった。
ガイマ・・・全てを他責にする。だが悪いやつではない。
トゥアーリ・・・クラスのムードメーカー。ちょっとずさんな性格。だがハレに好かれるため、マメな男になれるよう奮闘中。
ハレ・・・クールビューティ。
心が枯れている、ハレ
ハレにとって、毎日はつまらなく、全てがグレーに見えた。
本当は昔は好きなことがあった。それは歌を歌うこと。よく両親に向かって歌を披露して褒められることが何よりも嬉しかった。そして将来は歌手になることが夢であった。
しかし段々と成長して、世間のことを知るとそんな夢は叶うはずがないと思うようになってしまった。
少し離れたコンコルドという大きな街では、自分よりももっと美しく、そして歌もダンスもできる女の子がたくさんいるらしい。
そんな中こんな田舎に暮らしている自分が、それに全てにおいて劣っている自分が、歌手になれるはずがない。厳しい現実を目の当たりにしてから、なんだか全てにおいてやる気がなくなってしまった。
昔は歌を歌うためには、宿題や家事をテキパキとこなし、自由になったら歌の練習をしていた。
しかし今は全てにおいてやる気が出ず、まさに無気力状態であった。
歌を歌うこともしばらくしていない。なんだか歌うこと自体も怖くなってしまっていた。
歌手になることはできない、その現実を受け入れなければいけない気がしていて、ひどく怖くなった。
次第に、そんな歌手みたいな夢を抱くよりも、真面目でコツコツと働く人と結婚して、自分は家のことをした方が、よほど建設的な将来に思えてきた。そんなことをクラスメイトのミドについ先日話をしたところであった。
小川のそばで
歌手になるより、もっと堅実な道を歩んだ方がいい。そうは頭では理解したつもりなのに、なぜかハレの心は晴れなかった。
授業が終わって、家路につく際、学校の近くの小川に差し掛かり、そこに腰を下ろした。
この小川はハレにとってお気に入りのスポットであった。川がさらさらと流れているのを見ると、心が落ち着いた。心がざわついた時はここにきて、精神を浄化させるのであった。
そうしてしばらく川を見ていると、後ろに人の気配を感じた。
振り返ってみると、トゥアーリがそこにいた。心配そうな顔でこちらを見ている。
「おー、どうした、ハレ。元気なさそうじゃん」
ハレの顔を見ると、パッと表情を明るくさせ、様子を聞いてきた。
「別に、、、あんまりよくはないわよ。ただボーとしているだけ」
そうかぁと言って、トゥアーリはハレの横に座った。
「なんか考えていたんじゃないの?」
そう聞いてきたトゥアーリにハレは答えた。
「うーん、将来のこととかかなぁ。」
「将来のこと?」
「そう。あたしね、子どもの頃は歌手になることが夢だったの。歌を歌って両親が喜ぶのが好きでね。でも最近はその夢を諦めたの。だって、もっと歌が上手い人なんていくらでもいる。そんな中あたしがトップになれるのなんて無理だって」
それを聞いてトゥアーリは悲しい顔をして、言った。
「そんな簡単に諦めるなよ。お、俺もハレの歌、好きだぜ。音楽の授業でも一番上手いじゃんか。きっとなれるって」
トゥアーリの顔は心なしか赤くなっているようだ。しかしそれにハレは気付かず、答えた。
「どうだかねー。でもその夢を諦めてから、なんだか元気が出なくて、ため息ばっかり出るのよ。ハァ」
言った側からため息をハレはした。まさにとりつく島もないと言った感じであった。
それから無言の時間が流れた。こんな時、どんな言葉をかけてあげればいいんだろう。トゥアーリが必死で考えていると、教師のケイもやってきた。
何で選ばれるのか
「おお、ハレにトゥアーリ。デートかな」
ニヤニヤと笑って、ケイは近づいてきた。
「べっ、別にそんなんじゃないよ!」
顔を真っ赤にして、トゥアーリは否定した。ハレは死んだ魚のような目をして無反応であった。
「最近、ハレは元気ないね」
ケイもハレの様子には気がついているようだった。
「なんかハレ、歌手になる夢を諦めたんだってさ。それからなんかやっぱり元気が出ないみたい」
「どうして、歌手の夢を諦めたの?」
そのケイからの質問には、ハレ自身が答えた。
「だって、あたしより歌が上手い人、たくさんいるもの。その中であたしが選ばれて歌手になれるなんて、全然想像がつかない。きっと無理よ」
きっと無理よ、と言い終わった瞬間、さらに深い悲しみを、ハレは感じたようだった。
「まあ、確かに歌手になりたいっていう人はたくさんいるだろうからね。その中で一番になるのはかなり大変だろうね」
そんなことないよ、きっとなれるよ、と元気づけるかと思いきや、逆にケイはハレの意見に同調してしまったので、トゥアーリは驚いた。しかしその次の言葉の方が、トゥアーリを驚かすものだった。
「でも一番になる必要ってあるのかな?」
「え?」
その言葉にはハレも驚いたようだった。
「そもそもだけど、一番上手いって、歌が上手いってことを言っている?」
「そうだけど」
「じゃあ、歌が上手いってどういうことなんだろう」
ハレは少し考えてからケイに答えた。
「そりゃあ、音程がピッタリと合っていて、声も大きくて表現が豊かでリズム感がいい。それに容姿もよくて、ダンスとかもできれば最強だと思うわね」
「うーん、なるほど。ちなみに、ハレにとって、好きな歌手の人はどんな人なんだろう」
そう聞かれて、パッとハレの頭の中には何人かの歌手の顔が浮かび上がってきた。
まず一人目は卓越した歌唱力を持っており、どんな状況においても歌を上手に歌い切ってしまう、歌唱力に定番のある歌手であった。
二人目は同じく歌唱力はあるのだが、ファンとの絆を大事にする人で、そういった優しい性格が好きであった。
三人目は歌唱力はありつつも、独自の表現方法を模索し、周りに迎合せず、自分のスタイルを突き通している人であった。
それを考えていると、この三人にはある共通点があることがわかった。
「先生、あたし、すごく重要なことに気づいたかも」
ニヤリとして、ケイは質問した。
「それはなんだい」
「あたしが好きな歌手の人たちは、みんな好きなポイントは違うんだけど、”歌が上手い”っていう点はみんな同じなの。
でもあたしが好きなポイントはそこじゃない。それはある意味最低限クリアするポイントであって、好きな歌手の人たちにはそれぞれ好きなポイントが違う。
オールマイティにいろんな歌を歌えるところだったり、
ファンを大切にするところだったり、
自分のスタイルを追求することだったり、
みんな違うのよ」
そう言ったハレに、トゥアーリは困惑しながら呟いた。
「それってつまり、、、どう言うこと?」
ケイはニコリと笑いながら話した。
「ふふふ、ことわざで、”人は長所によって好かれ、短所によって愛される”ともいうね。別に歌手になりたいのだったら、歌が一番上手い必要はないかもしれない」
こくりとうなづいて、ハレは答えた。
「ありがと、先生。あたし、やっぱり歌手になる夢は諦められない。だって、歌を歌うの、好きだもの。歌の練習はきちんとして、それに加えてあたしらしさみたいなものがプラスできないか、考えてみるわ」
ニコリとハレは笑った。久しぶりの笑顔であった。
一本槍で行こうとすると、相当その長所が突出していないと、難しい。何との掛け合わせで行くか、それは続けてみないと、わからないのかもしれない。
以上

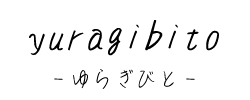








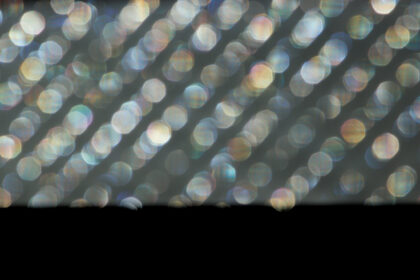

コメントを残す